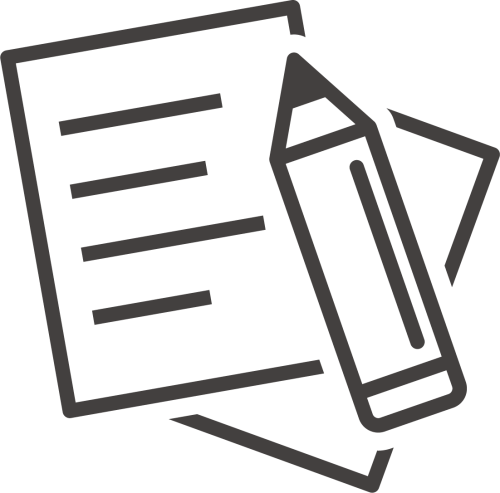Q&A
よくある質問をまとめました。下記の内容以外のご質問は、【contact】よりご質問ください。
建築士という資格は「一級建築士・二級建築士・木造建築士」の三種類です。
しかし建築士の資格を持った人の職業は実に多種多様です。
設計事務所・大工・現場監督・公務員・建材メーカー社員など、建設業界のさまざまな分野の方が資格を取得しています。
【建築士】という資格は、『設計監理を業として行う事のできる資格』です。ブランド的に捉えられている為、一定の受験資格を得れば、設計監理業務を行わない方も国家試験を受けて建築士となっています。
そこでまず誤解されがちなことがあります。
「建築士=設計が出来る」これは大きな誤解です。
「全ての建築士が同等の設計能力を有しているわけではありません」
私が鉋(カンナ)やノミを扱う事が出来ないように、それぞれ専門とする分野があります。 医者の専門分野に似た節があります。専業で設計を行っていない建築士へ設計依頼する事は、産婦人科の医師に鼻炎の診察を受けに行くようなものです。笑い話のようですが、こうして建てられる建物の実に多い事か・・・
また「一級建築士」の方が「二級建築士」よりも設計が上手いとも限りません。 一級と二級の違いは、設計監理業務が許されている「建物の規模」の違いであり、上手い下手は個人の資質の問題です。「知り合いに建築士が居るので、その人にお願いしよう!」とお考えでしたら、その建築士の専業を知った上で依頼する事をお勧めします。
設計と監理の2つの言葉から成り立っており、建築士の資格を有する者のみが業とする事が出来ます。
●設計
馴染みのある言葉ですので、特に説明の必要はないと思われますが、図面を描くのみが設計の仕事ではありません。 図面はあくまでも成果品の一つであり、そこに描き込む事を『考える』のが設計の主な作業です。
・建築主の要望を実現するプランとデザイン
・予算内の材料選定
・法的な規制への対応
これらに応える得る寸法やカタチを考えて図面化する作業が【設計】です。
●監理
一般的にあまり知られていない単語ですが、設計と監理は一体の関係にあります。
如何に立派な設計図を作成しても、設計者の考えた通りに工事現場で造らなければ「絵に描いた餅」です。
・設計図通りの施工が進んでいるかチェック
・図面だけでは伝わらない内容の伝達
・建築主の代理となって、工事現場との打合せや指示
・建築主への報告
これらの業務が【監理】です。設計者は工事が開始したと同時に「監理者」と呼び名が変わります。 建築主にとって監理者は、『工事現場の通訳』と『工事現場のチェック役』となります。 専門的知識を用いて、建築主の代理となって現場をまとめていきます。
現場監督(現場代理人)と何が違うかは、『工事監理と工事管理の違い』をご覧ください。
建築現場には「監理(かんり)」と「管理(かんり)」の2つの「カンリ」があります。
この2語の読み方は同じですが、役割や立場は全く異なります。
【工事監理】
一般的に設計事務所の「設計者」が監理者となります。
主な仕事は
○設計図通りの施工が進んでいるかチェック
○図面だけでは伝わらない内容の伝達
○建築主の代理となって、工事現場との打合せや指示
○建築主への報告
立場は『建築主の代理人』となり、監督業務といった立場です。
【工事管理/現場監督】
施工会社の現場代理人(現場監督)のことを指します。
主な仕事は
○工程管理(工程計画や施工順序の検討、大工などの職人の手配)
○材料管理(使用材料の発注や管理)
○安全管理(作業員と周辺住民等への安全確保)
○原価管理(請負金額内での材料費、人件費等の金銭管理)
立場は『工事現場を動かす責任者』です。
同じ「カンリシャ」ですが、役割も立場も全く異なります。
建築士法第2条6項に「その者の責任において工事を設計図書と照合し、それが設計図書の通りに実施されているか否かを確認する」と規定されており、工事現場へは必ず監理者を設けなければなりません。
昨今では設計施工の工務店やハウスメーカーによる現場では、監理者は名ばかりで機能しない状態の現場もあります。
なぜなら監理者は品質管理の為に、管理者の意に添わない指示を行う必要があるからです。
しかし設計施工一貫の会社では、会社の利益に反するケースが多く、監理者の立場に矛盾が生じてしまいます。
設計事務所が行う監理が、工事現場に必要なポイントがココにあります。
建築主の利益を基準にした指示は、時に現場監督と衝突することもありますが、そこに設計事務所の監理の価値があります。
まだまだ一般的に設計監理料への理解が得られていないと感じます。
ハウスメーカー等では「設計料¥0」と思われがちですが、はたして無料でしょうか?
もし無料だとしたら、子供の積み木のように考えることなく造られる建物なのでしょう。(辛口でゴメンナサイ)
日々積上げた専門的な知識を注ぎ込み、高額な建設費の責任を背負う仕事を、無料で行う人が居るのでしょうか?
設計監理料については国土交通省告示にて明示されていますが、残念ながら民間において
告示の記載内容では、設計監理料が高額になりすぎてしまい、民間での採用は困難です。
但し、その告示の額に匹敵する仕事内容である事は間違いありません。
一般的に扱われている設計事務所の設計監理料とすると、「工事金額の10%程度」と言われています。
2500万円の建物ならば、250万円の設計監理料が発生するということです。
さて、これを「高い」と思われるか?「安い」と思われるか?
まず「安い」と思われる方は少ないと思います。車一台買える額ですから。
では「高い」のかどうか。それは『設計士が設計監理料に見合った仕事をするか否か』だと思います。
図面を使い回したり、数回しか現場へ足を運ばなかったり、創意工夫が施されていないような仕事だったり、手を抜けば抜きたい放題の仕事でもあります。仕事ですから採算を無視した事は出来ませんが、この仕事に誇りを持ち、多少足が出ても「良い建物にして喜んで頂きたい!」という気持ちがあれば、自然と報酬額以上の労力を注ぎ込むことになります。それでも納得できる建物になり、喜んでもらえれば、報酬額以上の苦労は報われます。
当社の場合、住宅1軒に費やす時間は約1000時間です。時給換算して頂ければ、高いか安いかお解りになると思います。
しっかりした設計監理を行えば、建設費以上の価値のある建物とすることをお約束します。
建物1軒の図面全ての事を【設計図書】と呼びます。一軒の建物の為に何枚の図面を作成するかは、設計者により大きく異なります。少なければ5枚程度で「確認申請」へ添付する図面だけのケースもあります。
設計図書には3つの役割があります。
① 工事の為の寸法やデザインの表示
② 見積り時の資料
③ 工事契約時の契約書
あまり知られていませんが、③の『契約書となる』が大変重要です。
例えば5枚の図面で2500万円の工事契約を結んで家を建てたとします。5枚の図面でも役所の審査を通す事は出来ますが、果して5枚の図面の中に2500万円の内容が全て記載されているでしょうか?材料の等級・品質など図面に描いていない事は、施工業者へお任せということになります。施工業者が良心的で赤字覚悟で良い建物を建ててくれるような会社ならば良いのですが、当然ながら商売です。
建築関係の裁判で非常に多い事例が「図面が無い」というケースです。建築主が無くしたわけではなく、図面が描かれていないのです。こういったケースでは、図面無しに契約した建築主にも過失があります。
当社では、35坪程度の住宅で『60枚程度』の図面を作成します。
設計費は図面の枚数に比例しませんので、可能な限り省いた方が楽ですが、正確な施工が行われる為に検討した内容は全て図面を作成します。図面を基に1ランク上の検討をしていただける施工業者がいますので、設計以上の建物へ昇華させる一歩にもなります。
図面の多さは、正確な意図を施工会社へ伝える為でもあり、正確な工事金額の根拠でもあり、綿密な契約書となるから多いに越したことはありません。
図面の重要性を御理解下さい。
建築主の要望があれば、知り合いの建設会社でも構いません。
基本的には、設計図書完成後に建設会社数社(3社程度)に同時に見積もりをお願いし、提出された見積書の比較をして、建築主に選んで頂きます。
この選定方法を【相見積り】といいます。
相見積りの際には、建築主からの指定がなければ、当事務所の判断と実績等を考慮して、数社提案いたします。
日頃より地元の建設会社の実績、コスト、仕事のレベル等を研究しています。
「大会社だから安心。零細会社だからダメ。」という判断は、住宅建築においては間違いです。
「現場の人々が如何に気持ちを込めて工事してくれるか!」この一点に尽きます。
相見積りを行い、金額と建設会社の実績等を同時に考慮して、最終的には建築主に決定頂きます。
工事契約までの間は、一緒に建設会社の選定・交渉・値段調整等を行います。
どうぞご相談ください。
検討中の敷地へ同行してご相談に応じます。
敷地選びは家造りの上で、最も重要な作業です。
設計者の立場からは、「周辺環境と地盤状況」が気になります。
以前、敷地選定中の建築主様に同行した事があります。
「立地も広さも大変良いのですが、値段が安すぎる。ちょっと見ていただけますか?」
現場へ行って解ったのですが、「高圧線下地〔上空に高圧線が架かった土地〕」でした。
敷地にはそれぞれ【癖】があります。
一見大変条件の悪い敷地でも、建築の設計次第では、その癖を良い方向へ向けることも可能です。
WORKSに掲載している「大きな栗の木の下の家」や「風立つ丘の家」がその成功例です。
傾斜地で敷地とすれば悪条件でしたが、その条件を逆手にとった設計で平地では得られない空間を創造出来ました。
敷地の癖を如何に処理し、プラスへ変換するか。
設計の醍醐味です。(大変ですが・・・)
遠方の建築主とは、既に多くの依頼を請けさせて頂いております。
遠方からの依頼の際に、2つのケースが考えられます。
CASE1/建築主のお住まいが遠方の場合
軽井沢の別荘の依頼で良くあるケースです。
設計打合せはWEB打合せ(Zoom、Skype、LINE等)を主として行います。
工事開始後はクラウドとメールにて、建築主が常に現場の状況を把握出来るように「現場写真の共有」と綿密な「現場監理報告書の発行」を行います。
建築主の代わりに建設現場へ足を運び、建築主に安心して工事の進行を見て頂くように取り組んでおります。
CASE2/建設地が遠方の場合
建設地が遠方の際には、交通費の負担をお願いいたします。
建設地が長野県の東信地域でしたら、特に交通費は頂きません。
これまでの実績で、設計契約から数えると約1年必要です。
設計契約を結ぶまで1か月の方もいれば、1年の方もいらっしゃいます。
設計契約後は、基本設計3か月、実施設計3か月、工事期間6カ月で最低1年程度必要です。
家造りはほとんどの方が一生に一度の大事業です。
新しい生活へ心躍る気持ちはわかりますが、時間をたっぷり設けて、後悔のない家造りをお勧めします。